第3回 地域医療を学ぶなら自治医科大学〜特色ある教育と実践
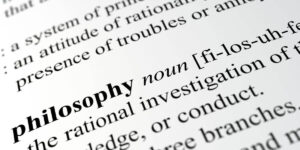
1. 自治医科大学の設立理念と、地域医療に特化した教育体制について
自治医科大学は、医療に恵まれないへき地などの医療水準の向上と、地域住民の福祉の増進を目的に、1972年設立されました。
患者一人ひとりに誠実に向き合い、高い診療能力を備えた医師の育成を目指すとともに、医学の発展や地域の健康・生活の質向上への貢献を使命としています。
単に医師不足を解消するためだけではなく、地域に根ざし、住民に寄り添った医療を実践できる人材の育成に力を入れている点が大きな特徴です。
2. 他の医学部とは異なる、自治医科大学ならではの教育プログラム(地域医療体験実習、僻地医療実習など)
自治医科大学のカリキュラムの特色は、全学年を通して地域医療に関する教育が体系的かつ段階的に組み込まれている点です。

1年次
医療の原点である「患者の視点」に立つ力を養うために、附属病院での早期体験実習や、地域で働く卒業生による講義の地域医療学概論などがあります。

2年次
特別養護老人ホームや地域包括支援センターでの実習を通じて、医療と福祉の連携や介護の現場を肌で感じる地域福祉実習があります。

3年次
臨床実習に向けた基礎的なスキルを身につける診断学実習に加え、知識と技能の定着を確認するCBT及びOSCEを受験します。

4年次
自治医科大学が誇る長期間のBSL(Bed Side Learning)が本格的に始まり、16の内科系診療科をローテーションしながら、患者さんの診療に主体的に関わることで、病態理解と臨床能力を深めていきます。

5年次
地域保健の中核を担う保健所での実習や、出身都道府県の地域医療機関で2週間の実習を行うCBCL(Community Based Clinical Clerkship)が組み込まれています。実際の診療に関わる先輩医師の姿に触れ、自らの将来像を具体的に描く貴重な機会となっています。
3学期からは選択必修BSLが始まり、これまでの実習で特に関心を持った診療科で、より主体的に、実践的な学びを深めます。

6年次
卒業後に勤務することになる都道府県拠点病院での実習が実施され、実際の職場での診療に備えます。
また、成績優秀者には「フリーコーススチューデントドクター制度」が用意されており、半年間にわたって自ら設計した研修プランのもと、国内外の病院や診療所での自主的な臨床実習が可能となります。
このように自治医科大学では、地域医療に必要な知識・技術・態度を、段階的かつ総合的に習得できる環境が整っています。全寮制による共同生活もまた、医師としての責任感や仲間との協調性を育む上で大きな意味を持っています。
卒業後も、大学と卒業生は強くつながり続けます。
へき地や離島など、医療資源が限られた地域で働く卒業生に対して、生涯教育の機会を提供し、常に最新の医療を提供できるよう支援体制が整えられています。
大学と卒業生が一体となって地域医療の質を高めようとする姿勢もまた自治か大学の大きな特色です。
3. 講義や実習を通じて、どのように地域医療への理解やスキルを深めたか
講義の中では、実際に地域の第一線で診療を行っている先生方からお話を伺う機会が何度もありました。
先生方は、限られたスタッフや設備の中でどのように診療を行っているのか、患者さんやそのご家族との関係性をどう築いているのかといった、地域医療ならではの実体験を具体的に語ってくださいました。
中には、救急対応から、在宅医療、地域住民との健康教室まで幅広く活動されている先生もおられ、地域医療の多面的な役割や奥深さを実感することができました。
そうした話を聞く中で、これまで漠然としていた地域医療というものを、より具体的にイメージできるようになり、医師が単なる医療提供者ではなく、地域社会の一員として信頼を築き、日常に寄り添いながら医療を実践している姿に強く心を打たれました。
こうした講義は、医学的な知識を学ぶだけでは得られない視点を私に与えてくれ、将来、地域で働く医師としての覚悟と責任を考えるきっかけとなりました。

実習では、大学付属病院での実習に加えて、地域の中核病院や診療所での実習も経験します。
これにより専門的な医療だけでなく、プライマリ・ケアの現場で求められる知識や技能を学ぶことができます。
大学病院での実習でも、自治医科大学の卒業生である先生方が多く指導にあたっており、実際に地域でどのように診察にあたっていたのか、限られた医療資源の中でどのような工夫をしていたのかを交えながら教えてくださるため、現場に即した学びが得られました。
特に、診察や検査の優先順位を的確に判断し、重大な疾患を見逃さないための考え方は、地域医療を担ううえで欠かせない視点であると実感しました。
4. 自治医科大学の教育プログラムで、特に地域医療の道へ進む決意を強くしたエピソード
先述したように、自治医科大学では、地域医療に携わる先輩医師や教員との交流を通じて、限られた医療資源のなかでいかに創意工夫して診療を行うか、そしてコミュニケーションの力がいかに診察の質を左右するかを学ぶ機会が多くあります。
ある地域医療に精通した先生の講義では、表現の仕方ひとつで、患者さんの理解や気持ちに大きく影響を与え、良好な医師患者関係を築く鍵となること、日常的なやり取りの中から病状への変化や生活背景を聞き出し、それを診療に結びつけることができることなどを学ぶことができました。
あたたかいコミュニケーションを持って住民に寄り添う姿は、私が将来目指す医師像そのものであり、地域医療に進む決意をより一層強くする経験となりました。
5. 自治医科大学で学ぶことの意義、卒業後のキャリアパスについて
自治医科大学で学ぶことの意義は、単に医師としての知識や技術を習得することにとどまらず、「どこで、どのように医療を提供するか」という視点を持ち、実践的に考える姿勢を養える点にあると感じています。
特に地域医療に重きを置いた教育を通じて、医療資源が限られた環境でも、住民の健康を守るために何ができるかを主体的に考える力が培われます。
卒業後は、出身地域を中心に地域医療を担う医師としてのキャリアを歩むことになりますが、それは単なる義務ではなく、自らの成と貢献を実感できる貴重な機会でもあります。
大学での学びと地域での実践がつながることで、自分なりの医療のかたちを築いていけるのではないかと思います。







